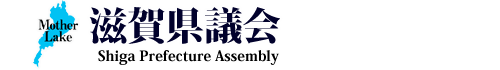滋賀県議会だよりWeb版 令和6年 9月定例会議
会議の概要
会期: 令和6年9月18日 〜 令和6年10月11日
会期:令和6年9月18日〜10月11日の24日間
9月定例会議では、本年6月、7月の大雨により被害を受けた箇所の復旧等のため、18億7,127万円を増額する「令和6年度滋賀県一般会計補正予算(第3号)」や、県立特別支援学校の新設に係る整備候補地の用地取得に向けた測量等のため、4,074万4千円を増額する「令和6年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)」など、知事提出議案76件と議員提出議案4件が上程されました。
これらを審議した結果、決算特別委員会を設置して休会中に審査することとした令和5年度滋賀県歳入歳出決算の認定議案等を除き、いずれも原案のとおり可決または同意しました。
また、各委員会では、付託された各議案、請願その他所管事項について審議および調査を行いました。
主な質疑・質問
【県政運営】
(問)
知事就任から10年を迎えられ、この間、新型コロナウイルス感染症の流行、物価高騰やインフレ、異常気象による災害の頻発、人口減少など、社会・経済情勢が大きく変化しました。知事は「健康しが」を旗印に県政を推進してこられましたが、来年度に向けた施策検討の方向性について伺います。
また、就任からの10年を振り返り、成果と課題を踏まえた上で、今後どのような政治姿勢で県政を進めていくのか決意を伺います。
(答)
令和7年度は、滋賀県基本構想における計画期間の折り返しを迎え、令和12年の目指す姿の実現に向けて、大切なものが変わらないように守ることと、しなやかに変わり続けることとのバランスをとりながら、未来につなげる行動を進めることができる一年にしたいと考えています。
また、「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」や「大阪・関西万博」を契機に生まれる有形無形の価値やつながりが、滋賀のレガシーとして次世代に引き継がれるよう部局横断で取り組むとともに、一人ひとりが輝き、「ひと」「社会・経済」「自然」のバランスが取れた持続可能な滋賀の実現を目指していきます。そのため、「子ども・子ども・子ども」、「ひとづくり」、「安全・安心の社会基盤と健康づくり」、「持続可能な社会・経済づくり」、そして「CO2ネットゼロ社会づくりやMLGs の推進」を施策検討の柱として、協働・共創の視点を大切に施策を構築していきます。
また、知事就任から10年、「未来へと幸せが続く滋賀」の実現に向けて県政に取り組んできたところです。この間、コロナ禍や物価高騰などの社会の変化への対応、災害等への強靭性の確保、地域公共交通の充実など、くらしを守り、未来へ希望をつなぐ取組に注力してきました。今後、より長期的な視点を持ち、新たな課題にも対応しつつ、持続可能な県政運営を推進し、誰もが自分らしく幸せを感じられる滋賀県を、そして誇りを感じ、住み続けたいと思える滋賀県を、包摂性と寛容性、対話と共感・共創を大切に、県民の皆様とつくっていきます。
【高等専門学校】
(問)
県立高専の初代校長予定者が元京都大学理事・副学長の北村隆行氏に内定したことが発表されましたが、初代校長の人選の際の観点および期待することについて見解を伺います。
また、教育の質を左右する教員の人選についても見解を伺います。
(答)
県立高専の校長は、学校の舵取り役となる重要な存在であることから、高いマネジメント能力やコミュニケーション能力、さらにはエンジニア教育への高い見識や情熱などを重視しながら人選を進め、北村氏に内定しました。北村氏には、これまで培ってこられた知識、経験、人脈などを存分に発揮し、開校に必要となる優秀な教師陣を確保いただき、学生や地域に寄り添いながら、知(知識)と行(行動)のバランスに優れ、成長意欲あふれるエンジニアを育成していただくことを大いに期待しています。
また、教員の人選については、高校生年代の指導に関する知見や研究のみならず、教育手法に長けた教員を確保していくことが重要であると考えており、こうした視点を持ちながら、全国に広く人材を求め、必要な教員を計画的に人選・採用していきます。
【文化】
(問)
彦根城の世界遺産登録に向けて、この一年間の取組状況と知事としての活動状況を伺いま
す。
また、世界遺産登録を含めた滋賀の文化振興について、文化庁に長く在籍され、7月16日に新しく副知事に就任された岸本副知事に思いを伺います。
(答)
令和5年9月の事前評価申請書の提出後、文化庁と連絡を密にとりながら、推薦書素案の作成に向けた作業や、機運醸成などを鋭意進めてきたところです。私自身としても、シンポジウムや国会議員勉強会で強い思いを伝えるとともに、文化庁長官にも直接、令和9年度の登録に向け更なる支援をお願いするなど、先頭に立って登録推進に取り組んできました。
また、本県では、滋賀県文化振興基本方針に基づいた取組を進めてきており、それらを引き続き推進した上で、県外から来た副知事として自分なりの気付きをお伝えしながら魅力発信に努めます。特に、彦根城の世界遺産登録については、文部科学省や内閣府等での経験や人脈を生かしながら、関係の皆様と一丸となって取り組みます。
※ 「事前評価申請書」
世界遺産登録をめざす資産について、推薦書の本提出前に、顕著な普遍的価値などについて、ユネスコの諮問機関であるイコモスより技術的・専門的助言を受けるための申請書のこと。イコモスとの対話を通じて、質の高い推薦を促すことを目的としている。
【琵琶湖保全】
(問)
現在、「第2期琵琶湖保全再生計画」の期間中ですが、琵琶湖の重要性や保全・再生の必要性について伺います。
また、固有種の減少や外来種の増加など、琵琶湖を取り巻く諸課題にどのように取り組んでいくのか伺います。
(答)
琵琶湖は、多数の固有種が存在する豊かな生態系を有し、貴重な自然環境や水産資源の宝庫として、その恵みを国民が等しく享受しており、まさに「国民的資産」だと認識しています。この国民的資産である琵琶湖を、健全な姿で次世代に継承していくことが我々の責務であり、総合的な保全および再生は、世界の先駆けとしての事例となり得るものと考えています。
また、琵琶湖の課題は複雑化・多様化し、森-川-里-湖における「生きもののつながりの維持」や、豊かな生態系と良好な水質の両立に向けた水質管理手法を構築することが求められており、漁業や林業などの現場の声や、住民や関係団体の意見を踏まえながら、庁内外の研究成果や科学的知見を活用していきます。加えて、琵琶湖を「守る」ことと「活かす」ことの好循環を創出するためには、多様な主体との協働の取組を更に発展させることが重要であることから、琵琶湖保全再生法制定10周年の節目となる令和7年度には、国や市町、下流府県市、関係団体等との連携を更に強め、琵琶湖保全再生計画の改定を行い、課題解決に繋げていきます。
【子ども・若者】
(問)
「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が改正され、子どもの現在の貧困を解消するとともに、将来の貧困を防ぐことなどが基本理念として掲げられたことを受け、本年度改定予定の「淡海子ども・若者プラン」についても更なるブラッシュアップが必要と考えますが、見解を伺います。
また、子ども・若者の貧困対策を実効性あるものにするための市町との関係強化について、今後どのように進めていくのか伺います。
(答)
7月に本県で開催しましたフォーラムにおいて、子どもたちから「家庭で十分な食事がとれない」などといった声を聴かせていただいており、施策を構築するに当たっては、当事者の声を丁寧に聴くことの大切さを再認識したところです。次期プランについては、子どもが権利利益を害され社会から孤立することがないようにするという改正法の目的を踏まえ、より実効性のある計画となるよう検討を進めていきます。
また、子ども・若者の貧困の解消に向けては、今回の法改正を受け、その意義や施策の方向性を市町と共有することが不可欠なことから、県市町子ども政策推進会議などの場を通じて対話を重ね、共通理解を深めるとともに、民間団体とも力を合わせて、地域の実情に応じた支援体制の強化に取り組んでいきます。
【農業・水産業】
(問)
現在、次期「滋賀県農業・水産業基本計画」の策定準備を進めていますが、次期計画は、琵琶湖システムが世界農業遺産に認定されて初めて策定される基本計画であり、今後の本県の農業・水産業の方向性を示す重要な計画です。策定に向けた知事の決意を伺います。
(答)
農業・水産業は、生きていくために欠かすことのできない「食」をつくる礎です。一方、これらを取り巻く環境は、世界人口の急激な増加や食料生産の不安定化など、大きな転換期を迎えており、国においては食料・農業・農村基本法が改正されたところです。
次期計画の策定に当たっては、こうした情勢の変化を踏まえ、琵琶湖システムを有する本県として世界に目を向け、輸出やオーガニックなどにも果敢にチャレンジし、生産額の増加を強く意識しながら、担い手の確保・育成や付加価値の向上を進め、持続可能な本県農業・水産業の発展を目指す計画としていきます。
【教育】
(問)
県立特別支援学校の新設について、守山市金森町を候補地とした経緯・理由を伺います。
また、障害のある子どもたちが安全・安心に過ごし、学びの充実につながるよう、教育環境の整備を図っていく必要があると考えますが、どのような特色のある学校としていくのか伺います。
(答)
特別支援学校の新設に当たっては、野洲養護学校と草津養護学校の大規模化対策として、スクールバスの乗車時間も考慮すると、両校の真ん中に位置する地域が適当と考え、守山市を軸に候補地の調査を始めました。また、大規模化の課題を解消するため、約3ヘクタールの必要面積を想定して、交通要件や周辺施設との連携等の観点から候補地を更に絞り込んだところです。特別支援学校の設置は、市の街づくりにも大きく影響を与えるため、守山市とも相談し、金森町を候補地として選定させていただきました。
同地で実現すれば、市民交流ゾーン等の施設や周辺環境の活用および市立・県立・私立の学校との連携による活発な交流活動が期待でき、地域と連携・協力しながら、子どもたちの成長を支え、地域の中で自分らしく生きる力を育む特別支援学校にしていきたいと考えています。
また、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、地域の皆様と共に取り組んでいける学校をつくっていきます。