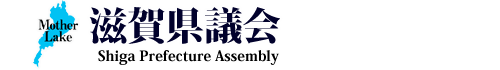���݈ʒu �F�g�b�v�y�[�W › �c���� › ���ꌧ�c����Web�Ł@�ߘa6�N�@11������c
���ꌧ�c����Web�Ł@�ߘa6�N�@11������c
��c�̊T�v
����F�@�ߘa6�N11��28���@�`�@�ߘa6�N12��20��
����F�ߘa6�N11��28���`12��20����23����
�@11������c�ł́A�ɐ��R�ɂ�����y���ЊQ���ۈ�l�ފm�ۂ̂��߁A23��4,557��7��~�z����u�ߘa6�N�x���ꌧ��ʉ�v��\�Z�i��6���j�v��A���̌o�ϑ�ɌW���\�Z�����p���A�u����������v�A�u�n��o�ς̐����v�A�u�����̈��S�E���S�v�ȂNji�ق̉ۑ�ɑΉ����邽�߁A251��4,998���~�z����u�ߘa6�N�x���ꌧ��ʉ�v��\�Z�i��8���j�v�ȂǁA�m����o�c��39���Ƌc����o�c��3�����������܂����B
�@������R�c�������ʁA����������Ă̂Ƃ�����܂��͓��ӂ��܂����B�܂��A9������c�ɂ����Čp���R�c�Ƃ���Ă����ߘa5�N�x���ꌧ�Γ��Ώo���Z�̔F������߂邱�Ɠ��ɂ��āA�F��܂��͉����܂����B
��Ȏ��^�E����
�y���X�|�E��X�|�z
�i��j
�@�킽SHIGA�P�����X�|�E��X�|���J�Â܂�1�N�����������ŁA������l�ЂƂ肪�g�߂ȂƂ��납��ւ���āA����グ�悤�ƌ����^���𐄐i����Ă��܂����A�����Q���𑣂���g�̐i�����f���܂��B
�@�܂��A�m�������N���@���ꂽSAGA2024���X�|�E�S��X�|���ł́A�V���Ȏ�g�����ڂł������A���N�Ɍ������m���̈ӋC���݂Ǝ���Ȃ�ł͂̎�g�ɂ��Ďf���܂��B
�i���j
�@�����ɂ����ẮA���̈��̂�X���[�K���A�����|�X�^�[�f�U�C�����L�������̊F�l������A��Ɠ��ɂ͐ϋɓI�Ɍ[�����s���Ă��������ȂǁA�����Q���̗ւ������ɍL�����Ă���Ƃ���ł��B���ݕ�W�����Ă���{�����e�B�A�ɂ��Ă��A��Ƃ��܂߁A����ɑ����̌����Q�����Ăъ|���A�u����v�u�݂�v�u�x����v���ꂼ��̗���ő��Ɋւ���Ă���������悤��g�����������Ă����܂��B
�@�܂��A���N�Ɍ����ẮA���ꂩ������p�����v�����g������炵���i��������ƂƂ��ɁA����܂ł���{������ɂ��Ă������z���⋤���Љ�̎����Ɍ�������g�A�����ĂȂ��Ɩ{���̖��͔��M�ȂǁA���ꂾ���炱���ł����g���ő���Ɋ�����������ڎw���Ă���Ƃ���ł��B�����āA���Ɋւ��S�Ă̐l���l�X�ȏ�ʂŎ���Ƃ��Č���P���A���⊴���A�A�ъ������L�ł�����ƂȂ�悤�����ɏ�����i�߂Ă����܂��B
�y�X�ѐ���z
�i��j
�@���i�ΐX�тÂ��茧���łɂ��āA����܂ł̎��ꌧ�̐X�ю{��ɂǂ̂悤�ȍv�������Ă����̂��f���܂��B
�@�܂��A���̂悤�ɓ��ʂɐł����Ă��邱�Ƃ܂��A���i�����ӔC�����闧��̒m���Ƃ��āA���ꂩ��̐X�ѐ���ɗՂތ��ӂ��f���܂��B
�i���j
�@����܂Ŗ{���ł́A���i�ΐX�тÂ��茧���ł����p���A����ꂪ�i�܂Ȃ��l�H�т���A�j�t���ƍL�t�������荬���������тւƗU�����A��������{�@�\������l���̌����}��ƂƂ��ɁA�Z��V�z���̍\���ނɁu�т�ށv�����p����x�������s���A���g���ӎ��̌����}���Ă����Ƃ���ł��B
�@�����I���Y�ł�����i����芪���{���̎R�X�́A���̐����ł���A�l�X�⎩�R�̉c�݂̌��ł��邱�Ƃ���A�f���炵������́u��܁v�����S�ȏ�ԂŎ�����Ɉ����p�����Ƃ���X�̐Ӗ��ł���ƍl���Ă��܂��B����́A�X�т̓K���Ǘ��A�ыƂ̐����Y�Ɖ��ɉ����A�_�R���n��̎��������������r�W�l�X�̑n�o�ȂǂɈ�̓I�Ɏ��g�ށu��܂̌��N�v����w�i�߂邱�ƂŁA�u�ǂ��c��v�Ƃ��āu��܁v�����S�Ȏp�Ōp�����Ă����܂��B
�y���N��Áz
�i��j
�@�����̏o�Y�ꏊ�̌���F���Ɖۑ�����Ɍ�������Ñ̐������̍l�����ɂ��Ďf���܂��B
�@�܂��A�����̂ǂ��ɏZ��ł��Ă����S�E���S�ɏo�Y�ł�����Â���Ɍ���������̌��ӂ��f���܂��B
�i���j
�@���N�x���{���Ă�������ɂ��ƁA�o�Y�ꏊ�ɂ��ẮA�n��ɂ���Ă͏\���Ɋm�ۂł��Ă���Ƃ͌����������܂��B�Ⴆ�A�o�Y�ꏊ���߂��ɂȂ��n��ɋ��Z����D�w�̏o�Y�ɂ�����o�ϓI�x����A�a�@����f�Ï��ɏ����ł��鉓�u�f�ÃV�X�e���̓�������������ȂǁA���Z�n�ɂ���Ď����ÂɊi���������Ȃ��悤�A�̐��\�z�Ɏ��g��ł����܂��B
�@�܂��A�o�Y�ꏊ������܂ł�艓���Ȃ邱�Ƃւ̕s����A�Y�O�E�Y��̐S�Ƒ̂̕ω��Ɋ��Y���A�S�Ă̔D�Y�w�Ƃ��̉Ƒ����A���S���ĐV���������}������̐�������Ă������Ƃ��d�v���ƍl���܂��B����́AICT�����p�������u��Â̐��i�A�����ĔD�w���f��Y��P�A���܂߂���q�ی��Ƃ̃l�b�g���[�N���������邱�Ƃɂ��A�����ǂ��ɏZ��ł��Ă����S�Ō��₩�ȔD�P�E�o�Y�E�玙���ł���Ƃ������S�������̊F�l�ɓ͂��Ă����܂��B
�y���グ�z
�i��j
�@�@��N��10��1�����猧���̍Œ�������A1,017�~�ƂȂ������Ƃɂ�錧����Ƃւ̉e���ɂ��Ďf���܂��B
�@�@�܂��A��ƋK�͂�Y�Ǝ�ʂ��킸�A���グ���\�Ƃ�����𐮂��邱�Ƃ��K�v���ƍl���܂����A�p���I�Ȓ����̈��グ�������ł���������𐄐i���邽�߂̍���̖{���̎�g�ɂ��Ďf���܂��B
�i���j
�@�����̏㏸���������A�Œ�����������グ���邱�Ƃ́A�����S�̂���グ����A����̊g��Ȃnjo�ς̍D�z�ɂȂ���Ɗ��҂�������ŁA�}���ȍŒ�����̈��グ�́A��Ɨ��v�̌�����ٗp�̗}���ɂȂ��肩�˂��A���ɁA�l����䗦������������Ƃ̌o�c�ւ̉e�������O����܂��B
�@�����������A�����I�Ȓ��グ���������邽�߂ɂ́A�R�X�g�㏸����K�ɉ��i�]�ł��Ē��グ�̌������m�ۂ��邱�Ƃ��d�v�ł��B���̂��߁A���ł́A�o�ϒc�̓��Ƃ��A�g���A���ߍׂ��ȏ��⎖�Ǝ҂Ɋ��Y�����T�|�[�g����ʂ��āA�~���ȉ��i�]�ł𑣐i���܂��B�����āA���̌o�ϑ�����p���Ȃ���A���Y���̌����V���Ƃ̓W�J�ȂǁA���Ǝ҂��s������������������g���㉟�����邱�ƂŁA�����I�Ȓ��グ�������ł�����Â���𐄐i���Ă����܂��B
�y�y�E��ʁz
�i��j
�@�����̂ǂ��ōЊQ���������Ă��ً}�ԗ����̒ʍs���\�ŁA�אڕ{���Ƒ��݂ɋ~���E���郋�[�g���m�ۂł���A�ЊQ�ɋ������H�l�b�g���[�N�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��f���܂��B
�@�܂��A����A�K�v�ȍ����m�ۂ��܂߁A�ЊQ�ɋ������H�l�b�g���[�N�̍\�z���ǂ̂悤�ɐi�߂Ă����̂��f���܂��B
�i���j
�@���H�ɂ́A�����Ȃ�ЊQ�ɂ����Ă��A�ԗ��̒ʍs���ێ������ƂƂ��ɁA������A��Ђ��Ă��v���ȕ������\�ƂȂ鎖�O�̑�⏀�������߂��܂��B1�̃��[�g���ʍs�~�߂ƂȂ��Ă����̃��[�g�ʼnI��ł��铙�A����ړI�n�ɑ��ď�ɕ����̃��[�g���m�ۂł���[���������H�l�b�g���[�N�̍\�z�����߂��A�����̗v���ɉ�������̂��A�ЊQ�ɋ������H�l�b�g���[�N�ł���ƍl���܂��B
�@�܂��A�{���̓��H�l�b�g���[�N�\�z�ɂ́A���������⌧�Ǘ����H�ő������Ɖ���v���ȃo�C�p�X�������K�v�ł��邽�߁A���̍����̊m�ۂ��d�v�ł��B��������ɑ��A���y���Չ���̐��i�Ɍ����������m�ۂ�A�ً}���R�ЊQ�h�~�ƍ̊��ԉ������������v�]���Ă����܂��B
�y�s�o�Z��z
�i��j
�@�u�ߘa5�N�x �������k�̖��s���E�s�o�Z�����k�w����̏��ۑ�Ɋւ��钲���v�̌��ʂɂ��ƁA�����̌��������w�Z�ɂ�����s�o�Z�������k���͉ߋ��ő��ƂȂ�܂������A���̌���ɑ���F�����f���܂��B
�@�܂��A����A�s�o�Z��ɂǂ̂悤�Ɏ��g��ł����̂��f���܂��B
�i���j
�@�q�ǂ��������w�Z�ŏ\���Ɋw��A�߂�������ł��Ă��Ȃ����A��Ϗd���~�߂Ă���A�q�ǂ��̎v���Ɋ��Y�����w�Z�̊��Â����A�w�Z���O�̊w�тƋ��ꏊ�̊m�ۂ�����܂ňȏ�ɐi�߂邱�Ƃ���ł���ƔF�����Ă��܂��B
�@�܂��A�����w�Z�ɂ�����s�o�Z��̎�g�̕������Ƃ��ẮA�@���R�h�~�ɂȂ����g�Ƃ��āA���ׂĂ̎q�ǂ������ɂƂ��Ė��͂�������S�ł���w�Z�Â�����s�����ƁA�A�x�ݎn�߂̎q�ǂ��ɑ��ẮA���Ɠ����������A�Z�X�����g�Ɋ�Â��A�X�̏ɉ������x����i�߂邱�ƁA�B�o�Z�͂ł��邪�����ɓ���Ȃ��q�ǂ������ɑ��ẮA�Z������x���Z���^�[�ł̊w�т̏�⋏�ꏊ�̋@�\���[�������A���S���ēo�Z�ł���悤�ɂ��邱�ƁA�C�w�Z�O�ɂ�����w�т̏�Ƃ��ẮA�Z�O����x���Z���^�[�̋@�\�[����}�邱�Ƃł���A����A�s������ψ���ƂƂ��Ɏ�g��i�߂Ă����܂��B
�y�����ɂ̂�����z
�i��j
�@�����ɂ̂���������ɓ������ẮA���߂���@�\���܂��A���݂̏ꏊ�ȊO���܂߁A������L�������Ƃ���ł���ƍl���܂����A�������f���܂��B
�@�܂��A���̑�K�͎��Ƃ����钆�A�����ɖ]�܂�錧���ɂ̎����Ɍ��������ӂ��f���܂��B
�i���j
�@���ꂩ��̌����ɂ�������ׂ��v�f�Ȃǂ܂��A���݂̌����ɂ̈ʒu�ɂ��Č����s���Ă����܂����A�����ɖ{�ق��@�Ǘ��Z���^�[�Ȃǂ̊��������̊��p��A�ٔ����⍑�̍s���@�ցA�W�c�̂Ȃǂ��������ӂɏW�ς��A�����ɂ𒆐S�Ƃ����܂����`������Ă������Ƃ����܂���ƁA�����_�ł́A���̒n���]�܂����ƍl���܂��B
�����ɂ́A���đւ����K�͉��C���K�v�Ȏ����������}���邱�Ƃ���A�����ɑS�̂ɂ��Ĉ�̓I�Ȍ����ɒ��肷��K�v������ƔF�����Ă��܂����A�������ւ̉e���Ƃ����ϓ_����A���������̒�����A����̑������ɂ��������S�̕������ɂ��Ă��������Ă����܂��B�����ɂ́A�����鎄�����݂̂Ȃ炸�A�͂邩�����̐���ւƖ��i�������p����Ă����ׂ����̂ł���A���ꌧ���̑��݈Ӌ`���ӎ����Ȃ��猧���̊F�l�ƂƂ��ɁA�V������������ɂÂ����ڎw���Ă����܂��B