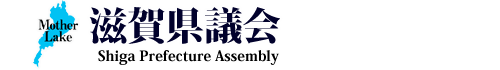滋賀県議会だよりWeb版 令和7年 6月定例会議
会議の概要
会期: 令和7年6月12日 〜 令和7年7月2日
6月定例会議では、デスティネーションキャンペーン実施に向けた準備や、高等学校等の授業料負担軽減対象世帯の拡大に要する経費のほか、国の内示を受けた公共事業費の追加等に係る経費など43億3,021万1千円を追加する「令和7年度滋賀県一般会計補正予算(第1号)」や、LPガスや特別高圧電力料金負担の軽減に要する経費に関し6億1,174万8千円を追加する「令和7年度滋賀県一般会計補正予算(第2号)」など、知事提出議案19件と議員提出議案4件が上程されました。
これらの審議の結果、いずれも原案のとおり可決または同意しました。なお、諮問案件1件については、知事の裁決案は適当と認めると答申しました。
また、各委員会では、付託された各議案、請願その他所管事項について審議等を行いました。
主な質疑・質問
【国スポ・障スポ】
(問)
いよいよ「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」が近づいてきました。全国から来訪される選手の皆さんが気持ちよく全力で戦える大会にしていただきたいと思います。
県では、令和6年4月1日に知事を本部長とする「レガシー2025創出推進本部」が設置されました。両大会をどのようにレガシーに繋げていくのか伺います。
(答)
国スポ・障スポの開催を一過性のものとせず、将来にわたって活かしていくため、庁内に部局横断の組織を設置して、レガシーの創出・継承に取り組んでいきます。
スポーツ振興では、大会で活躍した選手や指導者が滋賀の地に残り、子どもたちの指導をはじめ県民のスポーツ活動に貢献いただき、また、大会を支える多くのボランティアの皆さんには、引き続き、大規模大会等の様々な機会でご活躍いただきたいと考えています。
両大会を通じて得られる様々なレガシーは、スポーツの振興にとどまらず、観光・地域の活性化、そして滋賀の共生社会の実現を通じて持続可能なまちづくりにも資するものです。こうしたレガシー創出の取組を全庁挙げて推進することにより、「健康しが」の実現を目指していきます。
【戦後80年】
(問)
本年は、我が国にとって戦後80年という大きな節目の年です。戦争を知らない県民が9割近くを占める今、県として主体的に平和への取組を進めていく必要があると考えます。戦争体験者や遺族の高齢化により、戦争の記憶の風化が懸念される中、若い世代へ戦争の記憶をどのように繋いでいくのか伺います。
(答)
本県では、県立で平和祈念館を設置し、将来を担う小中学生等にも身近な地域での戦争の爪痕を知ってもらい、直接感じ、触れ、考えを深めることができる場を提供することにより、戦争の記憶を繋いでいるところです。
今年は戦後80年であることから、様々な「平和」について考える機会を提供し、特に次世代を担う若い世代が主体的に学び、自分事として考える力を育み、自ら行動する機会を広げることで、戦争の記憶を確かな形で未来へ繋げていきます。
【観光】
(問)
今年3月、訪日外国人数が過去最速で1千万人を突破し、4月には大阪・関西万博が開幕しました。万博開幕から2ヵ月が経過し、本県における観光誘客の動きを伺います。
また、5月には令和9年秋の(※1)デスティネーションキャンペーンの本県開催が発表されました。どのような方向を目指すのか、また、そのための推進体制と取組を伺います。
(答)
県内観光事業者向けのアンケート等では、万博を絡めた団体予約やインバウンドの個人客が増加したといった声をいただいています。また、事業者において、インバウンド需要を見据えた外国人向け宿泊プランや食事メニューの開発に取り組む動きも見られます。効果の広がりはまだ限定的ですが、万博での滋賀県デイや滋賀魅力体験ウィークの機会を活用した発信等により、本県への誘客に繋げていきます。
デスティネーションキャンペーンでは、更なる誘客に向け、7月を目途に幅広い分野の関係者とともに実行委員会を設置し、地域全体で観光振興を図る「観光まちづくり」を進め、地域経済の活性化はもとより、滋賀を訪れる方、滋賀に暮らす方、一人ひとりのウェルビーイングを目指します。
※1「デスティネーションキャンペーン」
JRグループが地域と連携して実施する大型観光キャンペーン。
【アユ漁】
(問)
(※2)「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」の公布・施行から10年を迎えましたが、昨年12月2日に解禁されたアユ漁の4月末までの漁獲量は過去5年平均の半分以下にとどまり、漁業関係者からは悲痛な声があがっています。「これまで経験したことのないような不漁」という状況を、どのように分析しているのか伺います。
また、アユ不漁に対する当面の対策と、水産業振興における長期的な琵琶湖の環境対策について伺います。
(答)
例年9月中旬から下旬がアユの産卵ピークとなりますが、昨年、県内の主な河川の水温が、アユの産卵に適した水温を上回る状況であったことを確認しており、9月の水温上昇がアユの産卵に影響を及ぼしたことが、不漁の一因ではないかと分析しています。
当面の対策として、来期に向けての産卵親魚が不足することから、人工河川に放流する親魚を当初の12トンに8トンを追加し、さらに放流時期を遅らせ、ふ化を分散させる新たな運用を行いたいと考えています。
また、長期的な環境対策として、関係部局による「いのちを育む琵琶湖を目指す検討会」において、知見を共有しながら対応策を議論し、漁場生産力の評価と回復に向けた技術開発などに取り組んでいきます。
※2「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」
平成27年(2015年)9月28日公布・施行。琵琶湖を「国民的資産」と位置付け、「豊かな生態系と貴重な自然環境及び水産資源の宝庫」としての幅広い価値をうたい、その恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会の実現に資することを目的とする。
【下水道】
(問)
本県全体の下水道普及率は、令和5年度末で93.0%に達し、全国でもトップレベルです。県民の安全・安心や、水源である琵琶湖の水質保全を図るため、下水道施設の改築更新や維持管理を適切に進めるとともに、南海トラフ地震などの災害にも備えることが必要だと考えますが、本県の下水道施設の老朽化の現状と課題をどのように認識し、どう対応していくのか伺います。
(答)
本県の下水道施設は、昭和57年(1982年)の供用開始以来、43年が経過し、その多くが耐用年数を迎え、大量の改築更新が想定されており、限られた予算・人員の中で、いかに効率的に事業を実施していくのかが課題と捉えています。
これに対応するため、施設を計画的かつ効率的に管理することが必要であり、中長期的な施設状態の予測やリスク評価に基づく修繕・改築計画を策定し対策を充実するとともに、耐震化を進めているところです。
さらに、効率的な施設運営のため、国が導入を推進している民間の知見や技術を活用した(※3)ウォーターPPPの導入についても検討を進めているところです。
※3「ウォーターPPP」
水道、工業用水道、下水道などの水分野における官民連携の新たな方式で、公共施設等運営事業(コンセッション)に段階的に移行するための「管理・更新一体マネジメント方式」と、コンセッション事業を併せた総称。
【県立高校】
(問)
私学も含めた、所得制限を設けない高校授業料無償化がいよいよスタートしました。学ぶ機会の確保や選択肢の充実に有意義だとされる一方、「公立離れ」が加速するといった懸念が指摘されています。本県における公立高校の果たすべき役割をどのように考え、高校授業料無償化にどのように対応していくのか伺います。
また、県立高校の魅力化の更なる推進をどのように進めるのか伺います。
(答)
様々な子どもたちのニーズに対応した多様な学びを提供することが、県立高校の役割だと考えます。大学や地域と連携した特色ある学びや専門的な学びにより、未来を担う人材を育成するとともに、学校と地域のつながりの中で地域活性化にも寄与し、地域づくりの観点でも重要な役割を担っています。子どもたちが行きたいと思える学校となるよう、魅力ある県立高校づくりに一層取り組んでいきます。
また、高校教育は、「答えを見つける」教育から「課題を見つけて解決に向けて考え行動する」教育の場となることが求められています。「地域連携」「高大連携」「多様な学び」などの取組を更に充実し、魅力と活力ある県立高校づくりを進めていきます。