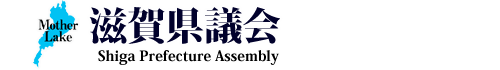滋賀県議会だよりWeb版 令和7年 9月定例会議
会議の概要
会期: 令和7年9月5日 〜 令和7年10月17日
9月定例会議では、新・琵琶湖文化館の整備や物価高騰への対応のほか、本年7月の大雨による被害への対応等のため、17億1,403万4千円を追加する「令和7年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)」など、知事提出議案36件と議員提出議案4件が上程されました。
これらの審議の結果、決算特別委員会を設置して休会中に審査することとした令和6年度滋賀県歳入歳出決算の認定議案等を除き、いずれも原案のとおり可決または同意しました。
また、各委員会では、付託された各議案、請願その他所管事項について審議等を行いました。
主な質疑・質問
【彦根城の世界遺産登録】
(問)
平成4年に彦根城が世界遺産暫定一覧表(※1)に記載されて以降、彦根市と滋賀県が登録に向けた取組を進めてきました。慎重に審議を積み重ねた上で、令和7年7月に文化庁に推薦書案を提出しましたが、国の文化審議会において令和7年度での推薦は見送られました。今後の彦根城の世界遺産登録に向けた決意を伺います。
(答)
250年もの長きにわたり平和な治世を続けた江戸時代の「大名統治システム」と、その統治拠点としてシンボルとなった城は、世界的に見ても普遍的な価値があり、彦根城がその代表となる城だと確信しています。
平成4年に暫定一覧表に登録されて以降、33年間にわたり取組を進め、あと一歩というところまで来ているのは間違いがなく、どんなことがあっても成し遂げるという気持ちは揺るぎないものです。
最短目標となる令和10年に彦根城の世界遺産登録を実現するべく、彦根市とともに全力で取り組み、引き続き、皆様のご支援、ご協力をいただけるよう進めていきたいと思います。
※1 「世界遺産暫定一覧表」
世界遺産条約を締約した国が、将来世界遺産一覧表に記載する計画のある物件を一覧にして、ユネスコに提出するもの。世界遺産委員会へ推薦書を提出し審査をされるためには、事前に暫定一覧表に記載されている必要がある。
【造林公社問題】
(問)
滋賀県造林公社は、昭和40年の設立以降、県内約2万haの森林を造林し、琵琶湖の水質保全や水源かん養機能(※2)の維持・向上等、重要な役割を果たしてきましたが、社会経済情勢の変化等により、非常に厳しい状況に陥っています。
令和6年9月に、分収造林事業(※3)のあり方検討会が設置され、今年度末までに県としての最終的な方針を決定すると聞いていますが、県が果たすべき責任と役割、その覚悟について伺います。
(答)
県が果たすべき責任として、一つ目は、将来世代に課題を残さず、造林公社問題の真の解決を目指す「県民への責任」、二つ目は、県内の森林に寄り添い琵琶湖や生態系と共に生きる「自然への責任」、三つ目は、将来的に森林の水源かん養機能を維持し、近畿1500万人の水源を守る「下流への責任」があると考えます。
この三つの責任を果たすため、森林に関わる県民、森林所有者、市町、下流自治体、企業などの協力を得ながら、県が主体的に取り組むことが重要と認識しています。
検討会で議論されている、県が保有する債権を放棄する、現在の公社組織を解散するといった方向性を踏まえ、議会でも十分に議論を重ねながら、道筋を示していきたいと考えます。
※2 「水源かん養機能」
大雨が降った時の急激な増水を抑え(洪水緩和)、しばらく雨が降らなくても流出が途絶えないようにする(水資源貯留)など、水源山地から河川に流れ出る水量や時期を調整する機能。
※3 「分収造林事業」
造林者(公社等)が土地所有者と契約し、その土地に苗木を植え、育て、将来森林が伐期に達した時に、その収益を両者で分収する制度。
【医療福祉拠点】
(問)
県庁に隣接する県有地に医療福祉拠点(※4)を整備するための検討が行われていますが、現時点で看護人材を育成する大学の誘致が思うように進まないなど、検討に長い時間を要しています。
大学の誘致には、大学の採算性や他の大学への影響などの懸念が残りますが、検討状況について伺います。
(答)
県内の看護師養成機関への支援の充実を図りつつ、医療福祉拠点における人材養成機能の整備を進めるため、今年10月頃を目途に再公募を行う方向で検討を進めています。
再公募の実施を念頭に置きながら、大学経営を取り巻く状況の把握や、近隣府県の私立大学に対する意向調査を行い、実現可能性を探ってきたところ、5つの法人から、拠点での看護学部開設に「関心あり」との意向が示されたところです。
少子化が進む中で新たな投資を行うことは、それぞれの法人にとっても大きな判断になると思いますが、将来の学生確保や採算性といった経営面も含めて十分な検討がなされた上で、事業参画いただくことを期待しています。
※4 「医療福祉拠点」
県庁西側の一団の県有地を活用して、在宅医療福祉等を推進するための医療福祉センター機能、医療福祉関係の人材養成機能を一体的に備えた拠点。
【ここ滋賀】(※5)
(問)
「ここ滋賀」は、首都圏に滋賀の情報を発信する拠点として、平成29年度に東京の日本橋に設置され、約1億円の家賃を含め、毎年度約2億円の予算を計上している大きなプロジェクトであり、開設以降、滋賀の豊かな食やモノ、歴史、文化など多様な魅力の発信に意欲的に取り組んでこられたところです。
「ここ滋賀」の今後の運営に向けたビジョンについて伺います。
(答)
「ここ滋賀」を「首都圏における滋賀のゲートウェイ(玄関口)」と位置づけ、東京から滋賀、滋賀から東京の双方向性の結節点として、次の三つの視点から機能強化を図りたいと考えます。
まず一点目は、マーケット機能の強化です。常設店舗だからこその機能を活かし、バイヤーとのマッチング機会の充実等、首都圏での販路開拓につなげていきます。
二点目は、関係人口(※6)創出拠点としての機能の強化です。コンシェルジュ(案内係)による案内・相談体制の強化、移住など様々なニーズへのワンストップでの対応等、関係人口の創出につなげていきます。
三点目は、情報発信の強化です。令和9年秋に実施予定のデスティネーションキャンペー(※7)ンを見据え、首都圏から滋賀への誘客につながるよう情報発信を強化していきます。
※5 「ここ滋賀」
平成29年に東京・日本橋に開設。特産品・伝統工芸品などの販売、地酒バー、滋賀の食材を使ったレストラン、イベント開催等により、首都圏で滋賀の魅力の発信と滋賀への誘引の役割を担う情報発信拠点。
※6 「関係人口」
移住や観光でもなく、日常生活圏や通勤圏以外の特定の地域と継続的かつ多様な関わりを持つ人々。
※7 「デスティネーションキャンペーン」
JRグループが地域と連携して実施する大型観光キャンペーン。
【地域公共交通】
(問)
地域公共交通の維持・確保は、喫緊にして不可避の重要課題であり、本県では、「誰もが、行きたいときに、行きたいところに移動ができる、持続可能な地域交通」を目指し、令和6年3月に「滋賀地域交通ビジョン」を策定し、その実現に向け、「滋賀地域交通計画」の策定が進められています。この計画の意義と決意について伺います。
(答)
減便・廃線により、免許返納者や車を運転できない学生の日々の移動が困難であるなどの課題が顕在化しています。地域交通を充実させ、これらの課題を解消していくことにより、例えば、「学生が行きたい学校を選択できて、通学が便利な滋賀」、「高齢になってもお出かけができて、生き生きと暮らせる滋賀」、「今後もまちのにぎわいが創出され、経済が活性化した魅力ある滋賀」を実現できると考えます。
「滋賀地域交通計画」は、このための計画であり、必要な施策や財源のあり方をまとめ、取組を着実に進めていくことで、「移動しやすく、暮らしやすく、豊かな滋賀」を実現していきたいと考えています。
【学校教育】
(問)
子どもたちは滋賀県の未来を担うかけがえのない存在であり、その学びの環境を整え、可能性を最大限に引き出すことは私たち大人の責務です。教育の現状を把握し、課題を明らかにする重要な手立ての一つが、毎年実施されている全国学力・学習状況調査です。
今年度の調査結果の分析を踏まえ、現在の状況をどのようにとらえ、今後どのように進めていくのか伺います。
(答)
今回の調査結果では、「人が困っているときは、進んで助けていますか」などの質問項目に肯定的な回答が増えた一方で、「自分にあった教え方、教材、学習時間などになっていましたか」などの項目に肯定的な回答をしていない子どもが一定割合いるなど、課題が見られたところです。
課題の改善に向けては、子ども一人ひとりの学力の状況を的確に把握し、基礎的・基本的な知識や技能を身に付けさせるとともに、子どもたちの「好き」を育み、「得意」を伸ばす授業づくりを、一人ひとりの先生が意識し、実践する必要があります。
引き続き、効果的な取組を一人ひとりの先生に確実に届け、必要な学習指導やさらなる授業改善を着実に実施していただけるよう、市町教育委員会とともに取り組んでいきます。